犬との旅行はいつから可能? その準備は子犬期から始まる!
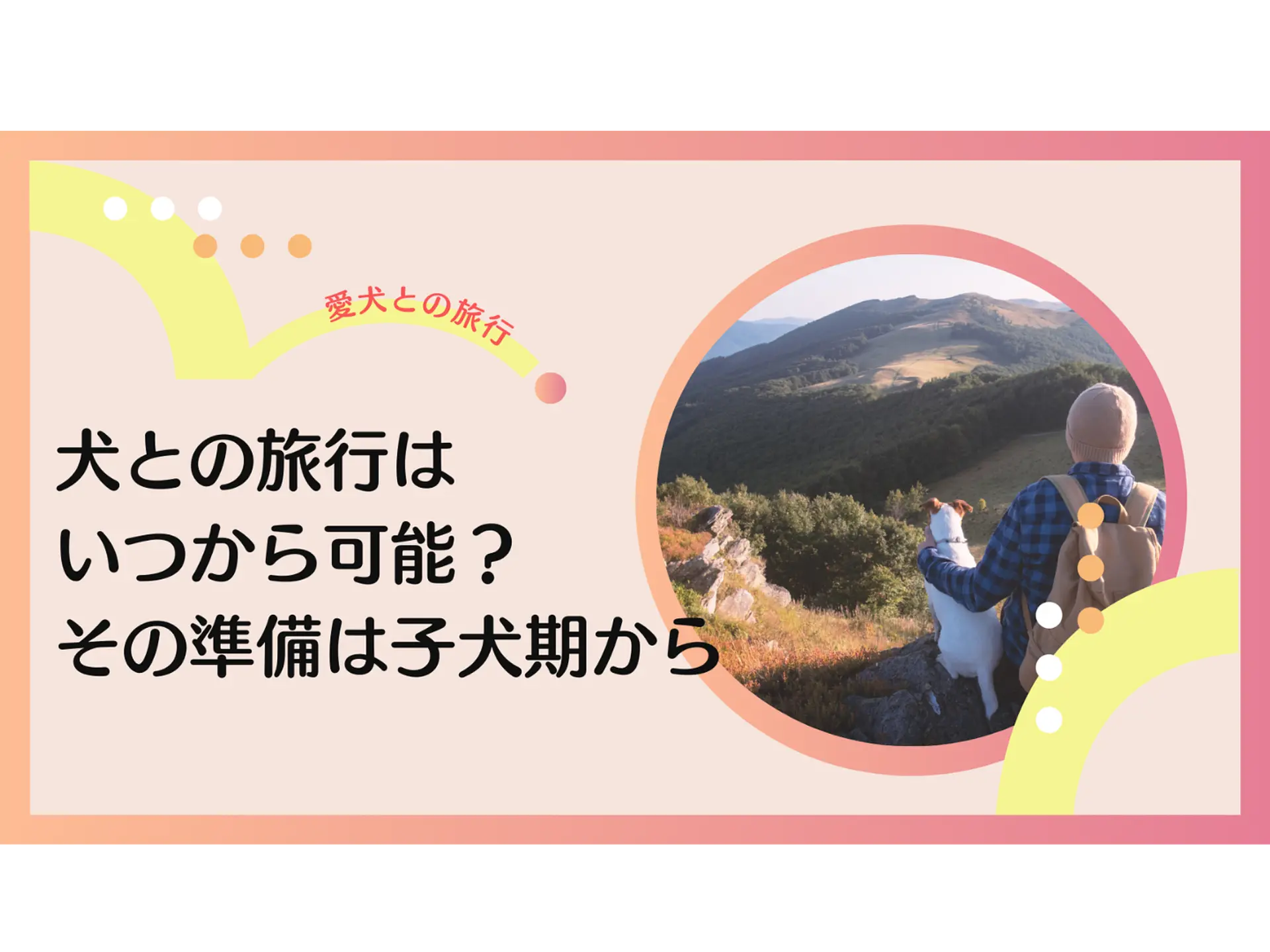
更新日: 2025年10月23日
愛犬は大切な家族の一員。できることなら大好きな旅行だって、いつか一緒に行ってみたい!と考える飼い主さんも多いのではないでしょうか。
そんなあこがれの愛犬との旅はいつから行って良いのでしょうか。また愛犬との旅に向けて知っておくべきこととは?この記事では、楽しくて安全な愛犬との旅に必要な準備や注意点などについてお伝えします。

犬との旅行のメリット/デメリット
そもそも、犬は自ら「旅行に行きたい」と言うわけではありません。愛犬連れで旅行に行きたいのは飼い主さんの思いであって、犬はそれにつきあってくれるだけです。犬はただただ飼い主さんと一緒にいたいだけですから。
だからこそ、犬にとっての負担を軽減できるよう考えたいものですが、その前に愛犬を連れて旅行に行くことのメリットとデメリットを考えてみましょう。
実は、このメリットとデメリットの中に犬との旅行に必要となる大事なポイントが隠されています。それを一つずつ見た後、最後に「犬との旅行はいつから行けるのか?」、その答えをお伝えしましょう。

愛犬と旅行に行きたい! そのための準備
何事にも準備は肝要です。その準備とは?…
ポイント①病気予防はできている?
旅行に行くとは、すなわち不慣れな土地、地域に行くということです。犬が注意を要する病気の中には伝染性のものや地域によって発生傾向が違うものもあり、また自然豊かな土地では野生動物や昆虫、節足動物などから感染する病気にも注意が必要です。
感染症
予防できる病気は可能な限り予防したいものですが、一つには各種感染症のワクチン接種が有効となります。愛犬のワクチン接種は完了していますか?
そのワクチンはいつからすればいいのかというと、世界小動物獣医師会(The World Small Animal Veterinary Association, WSAVA)では、「6~8週齢で初回のコアワクチン接種を行い、その後は2~4週間隔で16週齢またはそれ以降まで接種を行う」ことを推奨しています(*1)。
子犬の健康状態や地域の状況などにより若干違いはあるものの、日本の現状では3~4回程度の接種でワクチンを完了することが多いようです。
ワクチン接種が完了しない子犬を旅行に連れ出すことは病気感染のリスクが高くなるので控えてください。
また、成犬であってもワクチン接種直後は一旦免疫力が低下し、体調を崩しやすい上に、副作用が出ることもあるので、旅行に行くのであれば数日~一週間程度様子を見てからにすることをお勧めします。
【犬のワクチンの種類】
ノミ・ダニ
そして、ノミ・ダニの予防対策も大切です。ノミやマダニは当の犬が痒いばかりではなく、瓜実条虫の他、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、バベシア症、ライム病といった重篤な病気を伝番することがあるので定期的な予防を心がけましょう。
【ノミやダニに起因する病気】
ポイント②社会化には取り組んでいる?
犬は子犬期にいろいろな体験をすることで犬として生きていく上でのルールを学び、それが成長後の性格や行動にも大きく関係します。これを社会化と言います。
特に生後3ヶ月までの間がもっとも吸収力が高く、大切な時期になります。その後は徐々に警戒心が芽生えてくるものの、さらに社会化が必要とされる時期です。
社会化不足の犬はストレスに弱く、不安を感じやすいため、物事を過剰に怖がったり、不安が強ければ吠え続けたりと行動の問題が出やすい傾向にあると言われます。つまりは、犬との旅行には不向きとなってしまいます。
旅先には初めてのことが多く、大なり小なりストレスはあります。それをやり過ごして楽しい経験と感じるか、トラウマになってしまうか、社会化が大きなカギを握っていると言っても過言ではないでしょう。
ですから、愛犬と楽しい旅行をしたいのであれば、子犬期からの社会化に取り組みましょう。
ポイント③トイレトレーニングやしつけはどの程度できている?
トイレトレーニング
愛犬を旅行に連れて行くには、トイレトレーニングができていることは必須です。
その際、トイレトレーと言うよりも、トイレシート自体を「トイレ」と思わせるようにトレーニングしておくと旅先で排泄させる時に楽になります。
併せて、「シーシーは?」「トイレは?」などコマンドによって犬がトイレに向かうようトレーニングできると理想的です。
いつからそのトレーニングを始めるのかというと、それは子犬がやって来たその日から。そう、犬との旅行の準備はこの日からすでにスタートしているのです。
基本的なしつけ
いくら犬OKの宿やお店、観光地であっても犬が吠え続けたり、いたずらをしたり、ましてや攻撃的になる、あちこち排泄をするなど問題を起こせば顰蹙(ひんしゅく)をかってしまいます。それどころか宿泊や入店を拒否されることもあるでしょう。そうなると旅行も楽しいものではなくなってしまいます。
犬のしつけとは、人間と生きるにあたって最低限覚えてほしいルールを教えること。それは犬自身の安全を守るためでもあり、他者に迷惑をかけないようにするためでもあります。
「マテ」「スワレ」「ヤメ」「オイデ」など基本的なことは教えてありますか? 愛犬が吠えてもやめさせることができますか? 万一リードから外れても呼び戻しができますか?

ポイント④乗り物には慣れている?
犬と旅行に行くには車やバス、電車など乗り物を使用することになります。
犬は酔いやすい動物です。何の練習もなく乗り物に乗せれば酔ったり、それによってストレスを感じたりするかもしれません。最悪、乗り物に乗ることを嫌うようになってしまうこともあるでしょう。つまり、旅行には行けなくなってしまいます。
要は、犬が乗り物に乗ることを“楽しいこと”と思わせるようにすればいいわけですが、それにはトレーニングが必要です。
車の場合、最初はエンジンをかけずに車内でおやつやおもちゃを与えたりして数分程度過ごします。大丈夫そうなら時間を少しずつ長くし、次にエンジンをかけてみます。エンジンをかける時間も徐々に長くしていき、犬が音や振動に抵抗を感じていないようなら、数分程度近所を走ってみます。着いた先では散歩をしたり、遊んだりして、犬にとって“楽しいこと”をして過ごします。
このようなことを繰り返すと、車に乗ると楽しいことがあるとインプットされ、車に慣れやすくなります。最終的には車に乗るのが大好きで、どこまで走っても酔わなくなる犬はたくさんいるのでトライしてみてください。
しかし、トレーニングをしてもどうしても酔ってしまう犬はいます。この場合、動物病院で酔い止め薬を処方してもらうことが可能です(体重や体調のチェックは必要)。
そのような犬にとっては、酔い止め薬を使用することで車酔いというストレスから解放されることにもなるので、お困りの場合は動物病院でご相談ください。

ポイント⑤飼い主さんとしての自覚とマナーは大丈夫?
残念ながら、観光地において犬連れ観光客によるトラブルがないわけではありません。
犬が吠え続けてもやめさせない、他の犬とのケンカ、犬は立ち入り禁止の場所に入れてしまう、人に噛みつく、排泄で汚しても処理しない…など。
中には他のお客さんからのクレームが出て、犬連れの入店OKを撤回したお店もあります。せっかく犬と楽しめる場所を提供してもらっても、飼い主さんのマナー違反によってそれを狭めてしまうのは残念なことです。
飼い主さんの行動一つで犬と楽しめる環境を広くもすれば、狭くもするということを頭の片隅に置いていただければと思います。
愛犬との旅行はいつから行けるのか?
さて、最後に「犬との旅行はいつから行けるのか?」、その答えですが、「子犬が生後〇ヶ月になってから」というようにはっきりとは言えません。
この記事でお伝えしたように「上記のポイント①~⑤までがクリアできてから」が答えとなります。
犬との旅行は日常の延長。日々の健康管理やしつけを怠らずに、愛犬との旅行の日を目指してください。きっと良い想い出になるはずです。
参考資料:
(*1)世界小動物獣医師会(The World Small Animal Veterinary Association, WSAVA)「犬と猫のワクチネーションガイドライン」
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-Japanese.pdf

犬もの文筆家&ドッグライター 大塚良重