⽝が「吠える」ことをやめさせるには? 吠える理由やしつけ・対処方法
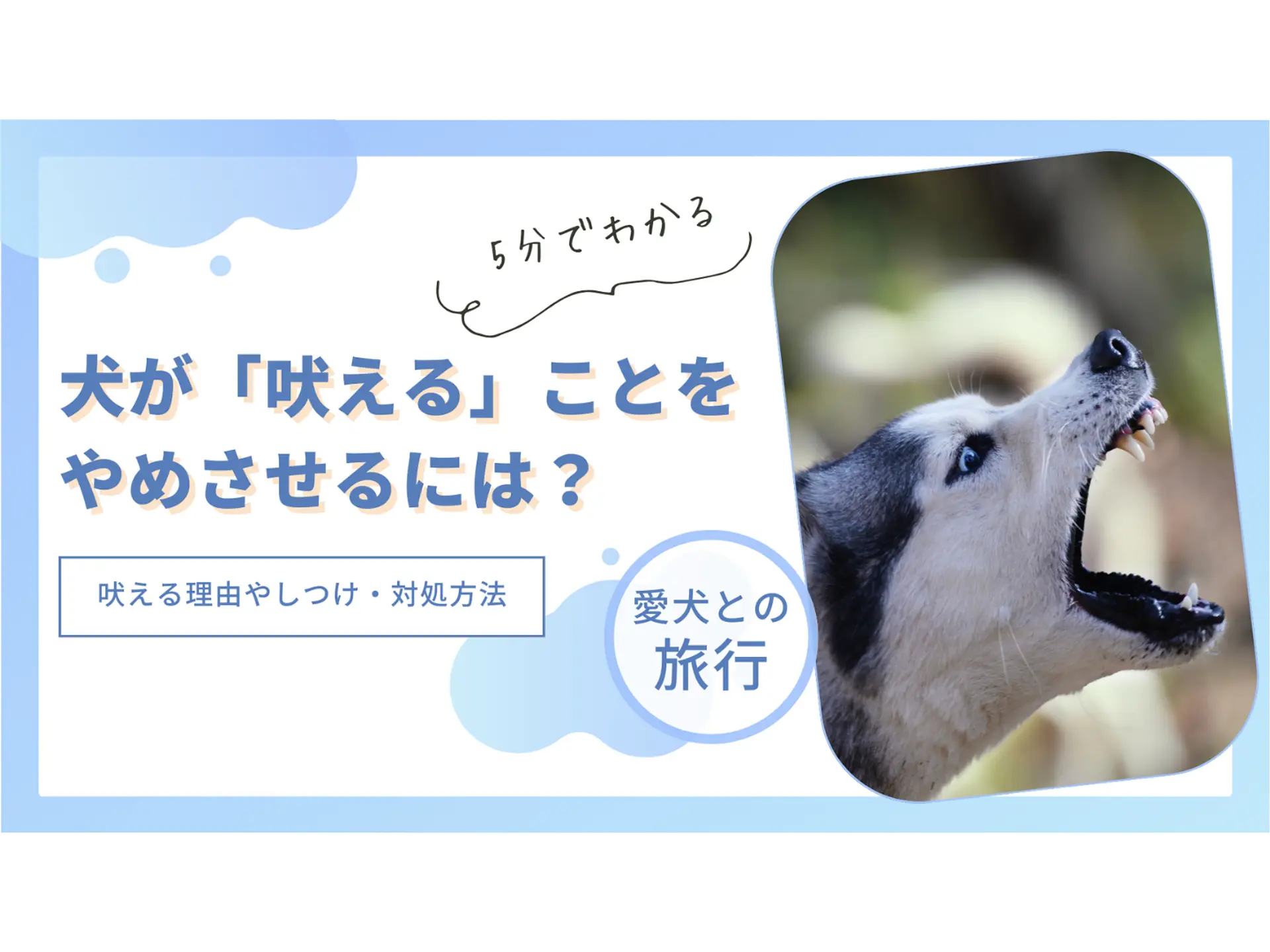
更新日: 2025年03月31日
犬が吠えるには理由がありますが、吠え過ぎや吠えてほしくないシーンで吠えられるのも困りもの。周囲にはたくさんの観光客がいる旅先などでも、できることなら吠えずに過ごしていてほしいものですよね。
では、どうしたらうまく“吠え”をコントロールできるのでしょうか。この記事では犬が吠える理由とその対処法をお伝えします。

犬が吠える理由
そもそも犬が吠えるには理由があり、厳密に言えばいわゆる“無駄吠え”というものは存在しません。
しかし、人間と暮らす以上、吠えられては困るシーン、吠え過ぎては困るシーンがあるのは確かです。
また、ずっと吠え続けていることは犬にとってもストレスになるでしょう。
やはり必要以上に吠えることはやめさせたいものですが、犬が吠える理由によって対処が違ってくるので、まずは犬が吠える理由には何があるのかを知っておきましょう。
犬が吠える理由①「知らない奴がいるぞ!」警戒
「誰かいるぞ!」「それ以上近寄るな!」といった感じで、他の人や犬、音、気配、物などに対し、警戒心や不安、恐怖などが入り交じり吠えることがあります。
昔から言われるテリトリー意識の強い“番犬”のイメージは、この吠え方でしょう。
犬が吠える理由②「ごはん、早くちょうだい!」要求
「ケージから出してよ!」「もう散歩に行く時間だよぉ!」など、犬なりの要求があり、飼い主さんに伝えたい時に吠えるパターンで、日常的によく見られます。
犬が吠える理由③「パパが帰って来た!」興奮
「ケン太君がいる! 一緒に遊べるぞ!」「いっぱい褒められちゃった!」など、犬が何らかに対して興奮した時に吠えるパターンです。
犬が吠える理由④「置いていかないで…」不安/分離不安
「留守番は嫌だよぉ…」「動物病院は好きじゃないんだ…」など、不安や恐怖から吠えることがあります。
「警戒」とは違い、不安が強いパターンで、最初は「クゥ~ン…」と甘えたような声を出すことが多くあります。
中でも、飼い主さんと離れることに強い不安があり、独りで留守番をしている時にずっと吠えているような場合は「分離不安」と呼ばれ、問題行動の一つにあたります。
犬が吠える理由⑤「痛いよ…苦しいよ…」痛み、苦しみ
ケガをして痛みがある時や病気があって苦しい時などに吠えることがありますが、この場合は、「吠える」より「鳴く」が近いでしょう。
犬が吠える理由⑥「散歩くらい行きたいし、イライラする!」ストレス
「たまには走ったり、遊んだりしたい!」「暇過ぎて、とりあえず吠えてみようかな」など、ストレスによって吠えることもあります。
その犬にとって何がストレスの元になるかはそれぞれですが、何も刺激がない環境もストレスになり得ます。
犬が吠える理由⑦「仲間かな? 血が騒ぐ」遠吠え
犬の祖先は仲間とコミュニケーションをとる時に遠吠えも使っていたことから、犬も本能的に遠吠えに近い音に反応することがあります。
犬が吠える理由⑧「なんだかわからないけど吠えている…」認知症
犬の寿命も延び、認知症になるケースは珍しくありません。認知症が進行すると意味もなく吠え続けたり、夜鳴きをしたりすることがあります。
犬の「吠え」をどうしつけ、対処する?
ここからは、吠えるのをやめさせるにはどうしつけたらいいのかを見ていきましょう。
「吠え」の問題への対処【環境づくり】
犬が吠える問題を対処するには、吠えにくい環境をつくることも大事です。
たとえば、外にいる人に吠えてしまうなら外が見えないように窓にカーテンを着ける、犬の居場所を玄関や窓から離すなど。
環境を整えるだけで吠えの問題が軽減する場合もあるので、吠えることばかりにとらわれず、環境を見直すことも時には必要です。
「吠え」の問題への対処【しつけ法】
これにはいろいろな考え方や方法があり、吠えている理由、犬の状況や性格によってしつけ方が違ってきますが、主に以下のような方法があります。
-
- 興味を他の“好きなこと”とすり替える
- 飼い主さんが反応しない
- 段階を踏みながら吠える原因に慣れさせる
- 大きな音を出す
(天罰方法と言われ、石を入れた空き缶のような音が出る物を吠えている犬の近くに投げる方法です。飼い主さんがやっていると犬に気づかせないようにするのがコツで、なかなかそううまくはいかない、かつ逆に吠えを悪化させる原因になりかねないため、現在ではあまり推奨されていません)

例1:おでかけ先で知らない人や犬に吠える場合(興奮/警戒)
外出先で他の人や犬に吠える時は、嬉しい気持ちがあり興奮して吠えている場合と、警戒して吠えている場合とがあります。
「1」のしつけ法を用い、まず、犬が好むおもちゃやおやつを用意しておきます。でかける時にはそれを持参し、犬が吠えそうになるタイミングを逃さず、おもちゃやおやつを見せて飼い主さんのほうに気が向くように誘導します。警戒吠えの場合はそのままその場から離れることで、犬が吠える原因を遠ざけることができます。
興奮して吠える場合も基本的には同じですが、おもちゃやおやつを与えながら「スワレ」や「フセ」などのコマンドを与えてもいいでしょう。ドッグランで他の犬と遊ぶことを楽しみにしている犬であれば、吠えずにおとなしくしていた後は、ご褒美として他の犬のところに行かせてあげるようにします。
例2:何かをして欲しい時に吠える場合(要求)
犬が何かを要求して吠えている場合、基本的には吠える原因となる犬のニーズを満たしておくことで吠えの予防をするのがベストではありますが、しつけ直しが必要な場合は「2」の方法を使います。
要求吠えでは、犬の要求に応えてばかりいると「吠えれば自分の要求が通る」と覚えてしまい、吠えが助長されることがあるので注意が必要です。
飼い主さんとしてはつい応えたくなるかもしれませんが、そこをぐっと抑えてその場から立ち去る。または何も反応せずにいることで犬がやがて吠えるのをやめ、静かになるのを待ちます。
静かになったタイミングで犬を褒め、ご褒美をあげてください。このように「騒ぐと何も起こらないけれど、静かにしているといいことがある」と覚えさせていきます。
ただし、この方法は自宅では容易にできますが、外ではなかなか難しいため、“その行動”を途中でやめさせる「ヤメ」のコマンド(合図、言葉)を最初に教えておくと、外出や旅行の時など役に立つでしょう。
例3:飼い主さんから離れると吠える場合(分離不安)
この場合は「3」の方法を使用し、ごく短い時間から犬が独りでいることに慣れさせていきます。
たとえば、部屋に犬だけを残し1~2分してから部屋に戻り、おとなしくしていられたら褒めましょう。この時、犬が好むおもちゃやおやつを仕込んだ知育玩具を置いておくと、それに夢中になることからおとなしくしていやすいです。
徐々に時間を長くして慣れてきたら、次は留守番の練習です。これも短い時間から始めますが、出かける時にはさりげなく玄関を出るようにし、帰宅した時に犬が吠えているようであれば犬が落ち着くのを待って、静かになってから声をかけるようにします。
なお、分離不安の状態が病的であるといった場合には、行動治療専門科の受診をおすすめします。
例4:しつけでは対応できない場合(病気・ケガ、認知症、ストレス)
犬が吠える理由が病気やケガにある場合は、元になる病気やケガを治すのが一番であることは言うまでもありません。
認知症は治すことは難しく、日光浴をさせて睡眠サイクルを整える、昼間はなるべく起こして夜眠るように仕向ける、室内に防音効果のある部材を取り付ける、サプリメントを使用する、などの対処法がありますが、吠えが重度の場合は抗不安薬や鎮静剤などの薬が必要になることがあり、その場合は動物病院でご相談ください。
また、ストレスが吠える理由になっている場合は、ストレスの元になっているものを極力遠ざける、逆にストレスの元になっているものに少しずつ慣れされるといった方法があります。
その他、運動不足や刺激不足がストレスに関連していることもあるので、散歩や運動を増やすことで問題が軽減されるケースもあります。
しかし、吠えがひどい、病的であるといった場合には行動治療専門科の受診が必要になるでしょう。

飼い主さんの一貫した態度も大切
犬のしつけをするには感情のままに怒らない、くどくど言わない、使うコマンド(合図、言葉)は統一する、タイミングを逃さない(褒めるタイミングは望ましい行動をとった1~2秒以内に)、飼い主さんは犬の導き手であるという意識をもつ、なども大切になります。
また、犬が吠える理由は様々。その理由によって対応の仕方も違ってきます。飼い主さんとしてはなぜ吠えているのか、理由を見極めて対応することがとても大切です。
たとえば、犬は痛みを訴えて吠えているのにそれを理解しない対応をしたならば、愛犬との関係性にも影響が出てしまうかもしれません。ですから、日頃から愛犬が発するシグナルを理解できるように努めましょう。
しかし、しつけがうまくできない時には、問題を抱え込まずにドッグトレーナーなどに相談するのもいいでしょう。
困った問題が解決できれば、普段の生活はもちろん、おでかけや旅行ももっと楽しくなるはずです。

犬もの文筆家&ドッグライター 大塚良重