八坂神社の白蛇弁天社にお参りして金運アップ!意外な歴史も再発見 【ぐんま観光県民ライター(ぐん記者)】
八坂神社と白蛇弁天社の由来
<八坂神社>
八坂神社の創建は不明ですが、平安時代に建てられたと言われています。御祭神は素盞嗚尊(すさのをのみこと)。江戸時代には牛頭天王として知られ、地元の人たちに親しまれてきました。

<白蛇弁天社>
白蛇弁天社は本殿の北側に鎮座しています。昔は神社の北東にあった弁天沼に祀られていましたが、後に現在の場所に移されました。
御祭神は、水の神である市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)です。音楽や金運、芸術や芸能の神様としてご利益があり、弁財天と同じとされてきました。蛇は弁財天の化身であり、金運アップの象徴と言われています。
世良田を見守ってきた神様たち
<群馬や近県の社>
本殿裏にある木々の中には、白蛇弁天社の他にも多くの小さな祠が佇んでいました。縁結びや交通安全、五穀豊穣など八百万の神様に参拝できます。さらに妙義や赤城、三峯の社など、近県や群馬に関連する神社の祠もあります。

<熊杉>
昔は仮に赤城神社にお参りに行くといっても、簡単ではなかったはずです。八坂神社は、地域の人たちにとって拠り所の一つだったのでしょう。祠が石で作られているのは、火事に備えるためだとか。先人たちの知恵が今も息づいています。
境内には、樹齢700年の熊杉の切り株もありました。残った姿からは、かつての荘厳さが感じられました。
清らかな空間に包まれたお参り
<手水>
朝の拝観時間になると、続々と参拝者が訪れてきます。参拝前に手を洗おうと手水に行くと、かわいい招き猫が浮かんでいました。手水から流れる水の音は、住宅街の中にある神社の静かな空間に、心地よく響きます。

<本殿>
お賽銭を入れて鐘を鳴らし、二礼二拍手一礼。神様に日々の感謝をしてきました。
長い歴史のある八坂神社には、神輿や神楽台があります。今は使われていないとのことですが、神輿殿では大小4体の神輿を拝観できました。
神社に秘められた歴史
<源氏の奥州征伐>
歴史ある八坂神社には、意外な建造物も多く現存しています。
宮司さんのお話によると「源氏の奥州征伐」の絵は、渋沢栄一ゆかりの渋沢家から 奉納されたそうです。参道のレンガも、渋沢家に関係するレンガ会社が作ったとも伝えられています。鳥居から本殿へレンガが使われている参道は、他の神社ではあまり見られません。

<賽銭箱>
お賽銭箱に取り付けられているのは、織田家の家紋「織田木瓜」です。八坂神社と織田家の関係は、南北朝時代までさかのぼります。後醍醐天皇の孫で世良田政義の娘から生まれた良王君は、尾張の神主になりました。後に八坂神社は尾張津島天王社から分霊され、織田家が参拝することになったと伝えられています。
白蛇様のお守りと動物たちの御朱印
<白蛇様のお守り>
お守りは厄除けや茅の輪守り、白蛇様の金運守りなどたくさんの種類があります。御朱印は「猫の日御朱印」や「戌の日御朱印」など、動物のイラストが人気。書き置きの干支や豊富な直書きの御朱印など、季節や好みに合わせて選ぶのもおすすめです。犬や招き猫、白蛇様など、かわいいおみくじも見ているだけで心が和みました。
さらに本物の白蛇様にも会えるかもしれません。じっと動かないときは置物のようですが、ゆっくり動く姿は神秘的でした。時期によっては冬眠しているとのこと。見かけた際はぜひ静かに拝んでください。

<猫の御朱印>
八坂神社は、長い歴史の中で多くの人たちを見守ってきた神社です。境内の白蛇弁天社は、脱皮を繰り返す蛇の姿に象徴される「再生」や「豊穣」、「金運」のご利益で、昔から信仰を集めてきました。白蛇弁天社や本殿での厄祓いで心身を清め、新たな始まりと良縁を引き寄せてみませんか。
<参考文献>
橋本憲一(昭和4).『新田郡名勝史蹟 : 御大典記念』p77-78.錦竜社
世良田村誌編纂会(昭和11).『世良田村旧蹟案内 2版』p9-10.世良田村誌編纂会
インフォメーション
八坂神社
住所:群馬県太田市世良田町1497
電話:0276-52-2969
営業時間:9:00~12:00、13:00〜16:00
定休日:不定休
駐車場:約30台
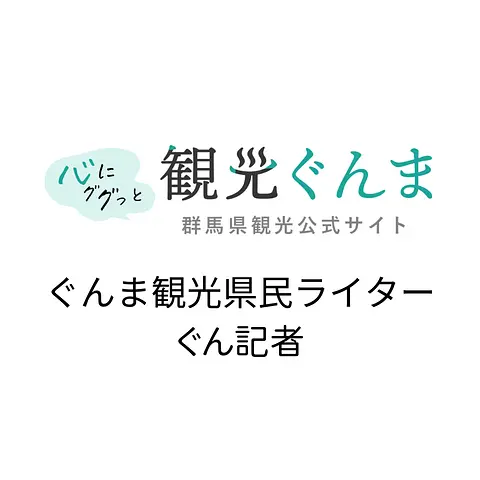
沙結月

